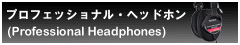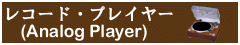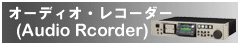File No.69 / 05
CD(コンパクトディスク)以前のディジタル録音(一般編)
実際の一般へのディジタルオーディオの登場は、かなり以前から存在しており、ビデオデッキとPCMプロセッサーでディジタル録音をするというような、かなりマニアックで機材も大変高価でした。
私はこのビデオデッキとPCMプロセッサーを使ってディジタル録音する方法に魅力を感じておりましたが、当時はビデオデッキでも15万円ぐらいしたのとPCMプロセッサーに関しては、20万円以上もするという大変高価な製品であったので、当時の私には購入することは出来ませんでした。

初めてビデオデッキとPCMプロセッサーを使用してディジタル録音したオーディオファンは、これまでには体験できなかったPCMのノイズのない音質に大変感動したものだと思います。
この時代は、ディジタル録音の規格が統一されていなかったので、PCMプロセッサーには12ビット、14ビットと16ビットが混在しており、後期になってCDと同じ16ビット仕様が標準化された模様です。
スペック的に見れば、14ビットの方が遥かに劣るように考えられますが、恐らく視聴上では音の差は、ほとんど分からないものだと思います。
また、初期のディジタル録音には最高のアナログ録音がベースになっているので音に全く細工がされておらず、大変素直な音が楽しめます。
音だけを考慮するとPCMプロセッサーの音質は、現在でも魅力があるオーディオ機器になると思います。
しかし、現在のような小型で簡単に高音質のディジタル録音ができる時代に、今では巨大といえるビデオテープにディジタル録音して記録することは、よほどのオーディオファンでないと無理な相談になります。
それでも、PCMプロセッサーの音質は、素直で素晴らしかったということは間違いないこという事実だけは記載しておきたいと思います。
PCMプロセッサーについて細かいことを言うと、当時はDA用のICが高価だったので1チップで左右に音声を振り分けているので、左右の再生音が僅かにずれるそうです。
しかし、視聴上ではほとんど認識できないレベルなので再生には問題ないそうです。
このPCMプロセッサーの左右のずれを修正してCD-Rを製作するという、とんでもなく頭の優れた方もいるようですが、修正すると音が変化するので、音質的に修正した方が良いかどうかは大変難しい判断になります。
そういうところがオーディオが難しく、面白いところだと思います。
でも、世の中には、凄い人がいるのだといつも感心させられます。
私の当時のPCMプロセッサーの記憶としては私の友人が、東芝のPCMプロセッサー一体型のVHSビデオデッキを購入したのを覚えています。
確か価格は、値引きしてピッタリ10万円だったと思います。
PCMプロセッサー一体型のVHSビデオデッキは、画期的なアイデアだったと思いますが、マニアックだったので、一般に普及することはありませんでした。
また、ビデオ内臓PCMプロセッサーが14ビットを使用していたので、基本的にホーム規格になってしまったために、他の一部のPCMプロセッサーを除いて互換性がなく、また互換性のあるPCMプロセッサーを使用しても、完全に対応できるかどうかは保証できません。
もともとPCMプロセッサーは、映像を記録するビデオデッキを利用することを前提として製作されているのですが、PCMプロセッサーにはビデオデッキとの相性が存在しており、相性の悪いビデオデッキとPCMプロセッサーを組み合わせると、ドロップアウトが頻発したりするような再生での障害が発生しますので全てのビデオデッキがPCMプロセッサーに使用できるとは限りません。
そのようなことが、PCMプロセッサーというものがオーディオで一層マニアックな存在になってしまったものだと思います。
このPCMプロセッサー一体型ビデオが潰れれれば、このビデオで製作したビデオテープを再生させることが難しくなるのがネックになります。
でも、このビデオのように斬新で挑戦的な製品をリリースしたことは、当時の日本のメーカーの開発意欲が手に取るように見ることができ、メーカーにとっても大変栄誉なとだったと思います。

現在の日本企業ように企業資本だけが大きいだけで、新しいものへ挑戦や開発意欲もなく、ほとんど全てを海外で設計・生産するような時代には考えられない製品です。
もう一度、日本のメーカーは、思い出になるような意欲的な製品を製作して欲しいものです。
(残念ながらグローバル至高主義には、このような製品の意味を永久に理解できないのだと思います。)
ディジタル録音の歴史について(1) つづく