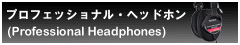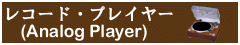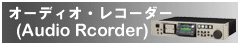File No.60 / 01
オーディオにおける音・音質の難しさ
オーディオは、良い音、良い音質を求める電気機器です。
良い音、良い音質と間違いなくいえるものは、自然界の音をそのまま再生できることなのですが、オーディオには電気的・機械的な制限を受けるので、自然界の音をそのまま再生することは不可能です。
そこで人の視聴できる帯域を基準にして、周波数帯域を2Hz~2万Hzまでを出来るだけフラットに再生することが、音が自然であろうと考えられています。
音には周波数特性だけでなく音の強弱があり、ダイナミックレンジという基準で測られています。
周波数特性は広い方が間違いなく理想なのですが、強弱のダイナミックレンジに関してはより広い方が良いものの、室内で使用するオーディオではあまり広くして再生すると音が巨大になりすぎ、たいへん聴きづらいものになります。
ホールなどの音を実際のダイナミックレンジと同じに再生すると小さい音から大きな音まで差がたいへん大きく、小さい音が聴こえにくかったり、大きな音が大きすぎると感じる場合があります。 (ほとんどのレコードなどの録音は、小さい音を持ち上げる調整をすることで、室内で聴いても自然に感じさせるように工夫されています。)
ダイナミックレンジについては、良い音、良い音質に関係するものの大変広いダイナミックレンジは室内ではなかなか活かせないものです。
あとオーディオの基本はステレオなので、左右のセパレーションが良いということは間違いありません。
その他、位相特性や音の立ち上がりの良さなど良い音の関係する要因は多数あると思います。
以上が全ての良い音、良い音質の要因とはいえませんが、スペック的にオーディオの音を考えた良い音、良い音質ということになります。
一応、最低限の音・音質の不自然さを感じさせないスペックがあることとして、良い音・音質について考えていきたいと思います。
オーディオの良い音、良い音質について、人の感性に影響する部分が大きくスペックだけでは現せない部分があり、良い音、良い音質というものの判断を大変難しくしています。
しかし、人の感性に影響するといっても、AMラジオ音源や電話の音のような周波数レンジが明らかに狭く、音や音質が良くないと感じられる音については除外して考えたいと思います。
オーディオは、様々な要素が加わるため、単純に『良い音、良い音質』という判断することが大変難しいものなのです。
良い音・良い音質の判断
そもそも音が良いというという判断の要素は、さまさまで多数あります。
クオリティの高い、クオリティの低い
レンジが広い、レンジが狭い
柔らかい、硬い
あたたかい、冷たい
低音が良い、高音が良い
解像度が高い、解像度が低い
ボーカルが良い、ボーカルが引っ込んでいる
弦楽器の音が綺麗、弦楽器の音が汚い
定位が良い、定位が悪い
位相が良い、位相が悪い
歪みのない音、歪っぽい音
低音がある、低音がない
繊細、荒い
滑らか、きつい
フラット、ドンシャリ
立体感がある、立体感がない
鮮明、不鮮明
美しい、汚い
音場が広い、音場が狭い
リアルがある、リアルさが欠ける
なんが好きな音、なんか嫌いな音(説明できない要素)
ざっと簡単にあげただけでも、多数あり、実際の音の判断になると、まだまだ足りなく、複合した要素も重なり合い複雑怪奇になっていきます。
また良い音と感じる要素は、低音がある、低音がないというようにハッキリと判断のできるものもありますが、なんとなく良い音に感じるというような説明出来ないような曖昧な感覚で判断になることも多くあります。
人の個人の感性というものは、実際には言葉では言い表せないのが普通ですが、便宜上言葉で表していることが多いのです。
良い音というような音の判断になると、人の感性の部分の言葉では表せない多くの部分を含みます。
例えばジミーペイジのオーバードライブのギターサウンドの音が良いといっても、どのように良いのか言葉だけではなかなか表現できないものです。
どんなにギブソンのオールドレスポール・ギターのサウンドが、良い音だと言葉でいっても、理解できるものではありません。

しかし、一度でもLED ZEPPELINのレコードを聴くと、ジミーペイジのギターサウンドの音の良さを実感できます。
そのような言葉で表せない部分が、オーディオにおける良い音の判断に存在します。
オーディオで良い音の判断の難しさは、人の感覚的な部分があるからです。
見えないから何も判断できないのではなく、誰でも音を聴くだけで確実に良い音と悪い音の判断ができてしまうのが、オーディオの不思議で楽しいところでもあります。