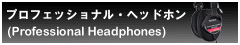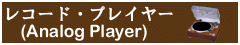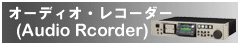File No.32 / 03
Technicsのオーディオの思い出
1980年代の日本のオーディオ知っている私にとって、Technicsのオーディオは意外に影が薄く、1980年代の日本のオーディオブームになったときに、多数のTechnicsのオーディオ製品がリリースされていましたが、あまりTechnicsのオーディオ製品に深い印象をもっていません。
しかしTechnicsというブランドのオーディオは、常に他社ができないような高性能な製品をリリースしていたことは間違いない事実です。
Technicsのオーディオをさかのぼれば1970年代になりますが、まず衝撃的だったのが高価なトランジスター式のコントロールアンプです。
多くのコントロールスイッチ類があるTechnicsのコントロールアンプです。
ハイエンド・オーディオの世界では、オーディオアンプにスイッチ類を多くつけるでコントロールすると、音質を阻害する歪が発生しやすくなるので、高級オーディオアンプでは敬遠されがちでした。
Technicsの高級オーディオアンプが、その常識を大きく破り、多数のスイッチ類でコントロールするオーディオアンプを登場させました。
このTechnicsのコントロールアンプが衝撃的だったのは、非常に多くのスイッチ類を取り付けられているオーディオアンプなのに、物凄く低歪に仕上げていることです。

当時のオーディオファンは、このTechnicsオーディオアンプの高性能さに驚かされたことでしょう。
流石、大手の一流企業の製作するアンプは、一味も二味も違うなと感心しました。 大手の企業には優れた技術者が多くいて、技術的な実力は半端ではないと感じた限りです。
私が始めてTechnicsのオーディオ製品の音を聴いたのは、同社の最高級スピーカーでした。 他にもTechnicsのミニコンポなども聴いていたかもしれませんが、ミニコンポに興味がなかったので全く覚えていません。
このスピーカーの特徴は、高音から低音までの周波数帯域をフラット再生にするというオーディオの理想を目指したスピーカーです。 特に低音の再生は、フラットに下まで伸びているのが特徴でした。
このスピーカーは、ウーハーが平面になっている特長があります。 後でわかったことですが、このウーハーは平面ドライブではなく、コーンスピーカーのコーンの曲面に発泡ポリエチレンを注入して表面に平面カバーを被せて平面駆動のように動作させていたようです。
オーディオ雑誌などでも、このTechnicsのスピーカーは良く紹介されていたスピーカーだったので、私はこのスピーカーにたいへん興味をもっていました。
たいへん高級なスピーカーなので、若かりしの私が購入できる代物ではありませんが、大型の電気屋さんに行けば視聴することができました。
大型の電気屋さんに行って、ついにこのTechnicsの大型スピーカーを視聴できる機会がきました。
そこで、私はこの超高級大型スピーカーの音の凄さを頭の中で想像して、期待に期待して視聴しました。
このスピーカーを視聴して驚きました。
こんな高級なスピーカーなのに音質が良く感じることができなかったからです。
低音は伸びているのかもしれませんが、コントラストのない不明瞭な音質で、全くベースに輪郭を感じません。
このTechnicsの高級スピーカーより安価なスピーカーの方が、全体的に遥かに良い音がするのです。
こんな高級なスピーカーから再生される音が悪い事を不思議に思って、そのときは帰宅しました。

帰宅してから私は、オーディオについて考えました。
オーディオでスペックがどんなに良くても、測定でどんな良い結果であっても、音質は実際に再生される音でしかわからないという結論になりました。
Technicsというブランドは大手の家電機器メーカーだけあって、どのTechnicsのオーディオ製品のスペック的は、たいへん優れていました。 しかし音は、長く地道にオーディオ専門しているメーカーの方が、技術的には劣っていても良いように思いました。
それから私は、Technicsというブランドに期待が薄くなり他のオーディオ専門メーカー機器の方に興味をもつようになりました。
あとTechnicsで私の印象に残っているのが、青い大型建具のようなスピーカーです。 価格もセットで500万円もする超高級オーディオです。
この大型スピーカーは、相当な製造技術をもっている企業しか製作できない製品で、流石一流企業しかできない製品と思いました。

P社の本社の前にあるのP社のミュージアムの創業者Mの歴史館に、この凄いスピーカーは傑作なので絶対に飾られていると思い、期待して来場させてもらったのですが、このスピーカーは展示されていなかったのでたいへん残念に思いました。
オーディオで評判の良かったTechnics SL-1200のダイレクトドライヴのターンテーブルは、知っていましたが正直あまり興味がありませんでした。
当時の日本のオーディオでは、ダイレクトドライヴのレコードプレーヤーは盛んで他にたくさん存在しており、Technics SL-1200よりで魅力のある製品が多かったからです。
私が、このTechnics SL-1200を知ったのは、Technics SL-1200が生産が終了してからで、たまたま知人が、このTechnics SL-1200を中古で購入したのがきっかけです。
ダイレクトドライヴのレコードプレーヤーは、好きだったのでいろいろなダイレクトドライヴのレコードプレーヤーの音の特徴は知っていますが、Technics SL-1200の特徴は全くノーマークでした。

Technics SL-1200の音の特徴を知人に教えてもらったり、Technics SL-1200の置いてあるレコードショップで自分で視聴して、Technics SL-1200の良さは何か理解することが出来ました。
長い間オーディオファンにTechnics SL-1200が評価された理由が理解することができました。
このTechnics SL-1200は、最高の音質のレコードプレーヤーとはいえないですが、比較的低価格のレコードプレーヤーのわりには、音のバランスがたいへん良く、さまざまなソースをオールマイティに再生することができます。
S字アームの癖も少なく、そのソースでもそつなく良い音で再生することができます。
Technics のダイレクトドライヴのモーターの性能が、たいへん良いからだと思います。
Technics SL-1200は、最高のレコードプレーヤーではありませんが、価格以上の高コストパフォーマンスの製品だといえます。
それが、多くのオーディオファンに長い間、Technics SL-1200が愛され支持されてきた理由だと思います。