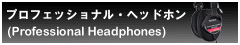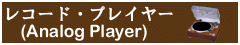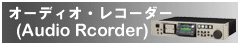File No.41 / 05
オーディオ機器の音を調整する最適なモニタースピーカーとは
私は、オーディオ機器の最終的な音の調整や音決めには、限りなくフラットなレスポンスの再生を考えて製作された4ウェイスピーカーが最適だと考えています。
4ウェイスピーカーになると高音と低音を分けるバイアリングなどの方法がありますが、そのように音を分けて再生するのではなく、2つの端子だけで完結している4ウェイスピーカーが最適だと思います。
高音のツイーターや中高音のスコーカーは、ハードドーム仕様で、中低音のミッドバスと低音のウーハーは紙素材でない丈夫なカーボンなどのハイテク素材が良いと考えています。
低音の音の癖が出ない密閉型あるいはアコースティク・エアーサスペンション型4ウェイスピーカーが良い。
オーディオ機器の音を調整する最適なモニタースピーカーのまとめ
■フラットレスポンスの4ウェイスピーカー
■バイワイヤリングでない4ウェイスピーカー
■アッテネーターのない4ウェイスピーカー
■中高音ユニットがハードドーム仕様
■中低音ユニットは、丈夫なハイテク素材が良い
■密閉型スピーカーが良い
■ホーンスピーカーは、オーディオ調整に向かない
■フラットレスポンスでない4ウェイスピーカー
フラットレスポンスのスピーカーは、各スピーカーユニットをフィルターで周波数ごとに切らなければならないので実際には実現不可能だと考えられます。
しかし、スピーカーを製作する上で低音から高音まで限りなくフラットなレスポンスを目指して製作することは、、癖のない自然な音を実現するための理想的な方法です。
フラットレスポンスでない4ウェイスピーカーは、現実的にには不可能かも知れませんが、理想のスピーカーを製作していく上で大変重要だと思います。
現実的に不可能でも限りなく周波数帯域をフラットな再生を目指した4ウェイスピーカーが、オーディオ機器の音の調整や最終の音決めに向いていると思います。
■バイワイヤリングでない4ウェイスピーカー
バイワイヤリングのスピーカーは、高音と低音の入力を分離させることが出来るので、高音部と低音部の影響が少なくできるために、高音部の音が薄くなったりなどの影響がなくなるので、理想的な方法だともいえます。
バイワイヤリングは、スピーカーをドライヴする理想的な方法なのですが、スピーカーを使用する側が最適な調整を必要とします。
最適な調整の必要性が、音を調整しなければならないオーディオ機器の音の判断を難しくしてしまいます。
オーディオ機器の音を調整しているのか?スピーカーの音を調整しているのか?が、分かり難くなり、どちらの音を最適にしようとしているのか難しくしてしまいます。
音の調整に使用するスピーカーは、あまり調整ができない方が良くオーディオ機器の音が調整がしやすいと思います。
■アッテネーターのない4ウェイスピーカー
スピーカーの音を最適にするアッテネーターですが、この調整があるとオーディオ機器の音の判断が難しくなってしまいます。
このことは、バイワイヤリングでない4ウェイスピーカーと同じ考えです。
音の調整したり音決めするスピーカーは、フラットレスポンスの4ウェイスピーカーが最適で複雑な構造なのですが、スピーカーの調整は限りなくシンプルな方が他の音が変わる要素を考えないで良いので、オーディオ機器の音の調整がやりやすくなります。
4ウェイスピーカーは、コンデンサーやコイルの組み合わせでネットワークが複雑になるので良い音が保つことが非常に難しい要素があります。
この音に対しての複雑な要素が良いオーディオ機器、特にオーディオアンプでは、コンデンサーやコイルにエネルギーを減衰させないで、エネルギーを供給できるかがアンプの真の実力になります。
良い音で再生することが難しい4ウェイスピーカーを、バランスの良い音で再生させることは大変難しいことです。
非力のオーディオアンプで4ウェイのスピーカーを再生すると、オーディオアンプなどの音の出方の弱い部分が大変良く目立ちます。
音の出方の弱い音の部分を強化していくことにより、どのようなスピーカーで再生しても優れた音質で再生できるオーディオ機器が製作できるようになります。
■中高音ユニットがハードドーム仕様
ソフトドームの中高音のユニットであれば、全体に滑らかな中高音を再生が期待できるのですが、音や音質を判断することを難しくしてしまします。
中高音のハードドームユニットは、音速が速くスピード感のある解像度が高い音を再生するので、音の違いが良く出るので音の判断がしやすいので機器の音の調整がやりやすくなります。
しかしハードドームは、一般に高音特性が良いのですがハードドームの特性上ピークが発生してしまいます。
ハードドームにはピークが為に、出来悪いオーディオアンプなどではピークの部分が目立ってしまうのでピーキーな音質になりがちになります。
ハードドームにあるピークの部分を上手く抑えて、バランスの良い音を再生させることがオーディオアンプの実力ということになります。
ハードドームは、解像度が良い反面、良い音で再生させることが難しいユニットになりますが、その部分を上手く抑えて良質な音質で再生できることが優れたオーディオ機器の条件になります。
■中低音ユニットは、丈夫なハイテク素材が良い
紙は、スピーカーのコーンの素材として優れた特性を持ちますが、コーン紙が大きくなってくるとコーンのねじれなど変形が発生するためにひずみが生じてしまいます。
このひずみをなくすために、コーン紙にカーボンを染み込ましたりして強化する必要があるのでコーン自体が重たくなり紙コーン特有の音の癖が出やすくなります。
強化された重い紙コーンのウーハーは、低音を多く出しやすいのですが低音の分解能が悪くなりやすくなる特徴があります。
強化カーボンやアラミッドハニカムなどのハイテク素材は、比較的低音の量感は少ないのですが分解能の良い解像度の高いクリアーで明快な低音が期待できます。
ハイテク素材は中低音を良い音で再生するのが難しい素材なのですが、この難しい素材をクリアーで明快な音で再生させることができることが、優れたオーディオ機器ということになります。
■密閉型スピーカーが良い
スピーカーには基本的に密閉型とバスレフ型のスピーカーがあります。
バスレフ型スピーカーは、ウーハーの後ろからでた低音を反転させて前面のダクトから放出することで低音を強化をはかれるので、密閉型スピーカーよりも低音の量感を得やすく、スピーカー製造メーカーの多くはバスレフ型のスピーカーを採用しています。
バスレス型スピーカーは、低音の量感を得れる反面、ある低音から急激に低音が低下してしてしまう特徴があります。
つまりバスレス型スピーカーは、低音が持ち上がる反面、最低域の低音のレベルが急激に下がるために最低音が出ないということです。
それに対して密閉型スピーカーは、バスレフ型よりも低音が出にくいのですが低音域がなだらかに下がる特性があります。
バスレフ型スピーカーは、低音の量感を得やすく、密閉型スピーカーは低音の量感は得にくい代わりに分解能のある素直な低音が楽しめます。
バスレフスピーカーは、低音の量感が得られるのでオーディオリスナーにとっては魅力がありますが、オーディオ機器メーカーがオーディオ機器を調整するのに利用するとバスレフスピーカーの低音の量感が、低音の解像度や質感の判断を難しくしてしまいます。
オーディオ機器の調整は、低音の解像度や質感が分かりやすい密閉型スピーカーあるいは、密閉構造で空気のバネを利用したアコースティック・エアーサスペンション型スピーカーが適していると思います。

■ホーンスピーカーは、オーディオ調整に向かない
ホーンスピーカーは、中高音のホーンの効果によってクリアーで解像度の高い中高音が楽しめるスピーカーです。
ホーンスピーカーで歌手のボーカルなどを再生すると非常に魅力的な良い音で再生されます。
しかし、この良い音と感じられるホーンスピーカーの特徴がオーディオ機器を調整するには向きません。
ホーンスピーカーで再生すると中高域の音が良く感じられるので、オーディオ機器の調整することが難しくなってしまうからです。
再生音が良く感じれるホーンスピーカーは、オーディオ機器本来の音を判断が難しくしてしまうのでオーディオ調整に向かないと思います。